ケラとはどんな虫?その正体、鳴き声、生態から対策までを徹底解説

「庭の土の中から、まるでモグラのような手を持った不思議な虫が出てきた…」 「地面の下から『ジー』という低い音が聞こえるけど、何の音だろう?」
もし、あなたがそんな経験をしたなら、その正体は「ケラ」かもしれません。
ケラは、コオロギやバッタに近い仲間でありながら、一生のほとんどを土の中で過ごすというユニークな生態を持つ昆虫です。その特殊な暮らしぶりから、農業では時に害虫として扱われる一方、土を耕してくれる益虫としての一面も持っています。
この記事では、そんな謎多き昆虫「ケラ」の正体から、鳴き声、不思議な生態、そして家庭菜園などでの対策方法まで、専門的な知見を交えながら分かりやすく徹底解説します。
この記事を読めば、ケラがどんな虫なのか、どう付き合っていけば良いのかが全て分かります。
もしかしてこの虫?ケラの正体と見分け方

まずは、あなたが見つけた虫が本当にケラなのか、その正体と見分け方から確認していきましょう。ケラは非常に特徴的な見た目をしているので、ポイントさえ押さえれば簡単に見分けることができます。
ケラの見た目の特徴【写真で解説】

ケラを見分けるための最も大きな特徴は、なんといってもモグラの手にそっくりな前足です。
| 部位 | 特徴 |
|---|---|
| 前足 | 土を掘り進めるために、太くシャベルのように発達しています。 |
| 体 | 全体的にずんぐりとした筒状で、茶褐色をしています。表面はビロードのような短い毛で覆われており、土が付きにくい構造になっています。 |
| 大きさ | 大人のケラは、体長 約27〜30mm ほどです[1]。 |
| 頭部 | 体に比べて小さく、硬い殻で覆われています。 |
このモグラのような前足を持つ昆虫は他にいないため、この点を確認すればケラだと断定して良いでしょう。
実はバッタやコオロギの仲間!ケラの分類
そのユニークな見た目から想像しにくいかもしれませんが、ケラは分類学上「バッタ目(直翅目)・ケラ科」に属する昆虫です[1]。
バッタやコオロギ、キリギリスなどと同じグループに分類されます。特にコオロギとは近縁で、英語では“Mole cricket”(モグラコオロギ)と呼ばれています。
「掘る・飛ぶ・泳ぐ」スーパー昆虫ケラの驚くべき生態

ケラは、その特殊な生活環境に適応するために、他の昆虫にはない驚くべき能力を持っています。熊本市動植物園では「スーパー昆虫」として紹介されるほど、その能力は多彩です[3]。
生態①:土を掘ることに特化した前足
ケラの最大の特徴である前足は、一生のほとんどを過ごす土中での生活に最適化されています。この強力な前足を使って地中にトンネルを掘り、巣を作って生活します。日中は土の中で過ごし、夜になると地表近くで活動することが多いです。
生態②:実は飛べる!灯火に集まる習性
意外に思われるかもしれませんが、ケラには立派な後ろ翅(はね)があり、空を飛ぶことができます。普段は折りたたまれて見えませんが、夜になると灯火(街灯や家の明かり)に引き寄せられて飛んでくることがあります[1]。「土の中にいるはずの虫が、なぜか家の網戸に…」という場合は、ケラが飛んできた可能性が高いです。
生態③:泳ぎも得意
ケラは水辺の湿った土壌を好むため、水に落ちてしまうこともあります。しかし、心配は無用です。彼らは水を弾く体の構造と、手足を使って器用に泳ぐことができます[1] [3]。まさに陸・海・空を制覇する昆虫と言えるでしょう。
ケラの鳴き声の正体は?

「ジー…」という地面から聞こえる不思議な音。昔の人は「ミミズの鳴き声」だと考えていたそうですが、その正体はケラの鳴き声です[1] [3]。
鳴き声の特徴と時期
ケラの鳴き声は、コオロギの「コロコロ」という音色とは異なり、「ジーーー」や「ビーーー」といった連続した低い音です。土の中で鳴くため、音がこもって聞こえます。
主に初夏から夏(5月〜8月頃)の、雨が降った後などの湿気が多い夜によく鳴きます。
鳴くのはオスだけ
他のバッタやコオロギの仲間と同じく、鳴くのはオスだけです。翅をこすり合わせて音を出し、メスへのアピールや縄張りを主張するために鳴いていると考えられています。
ケラは益虫?害虫?
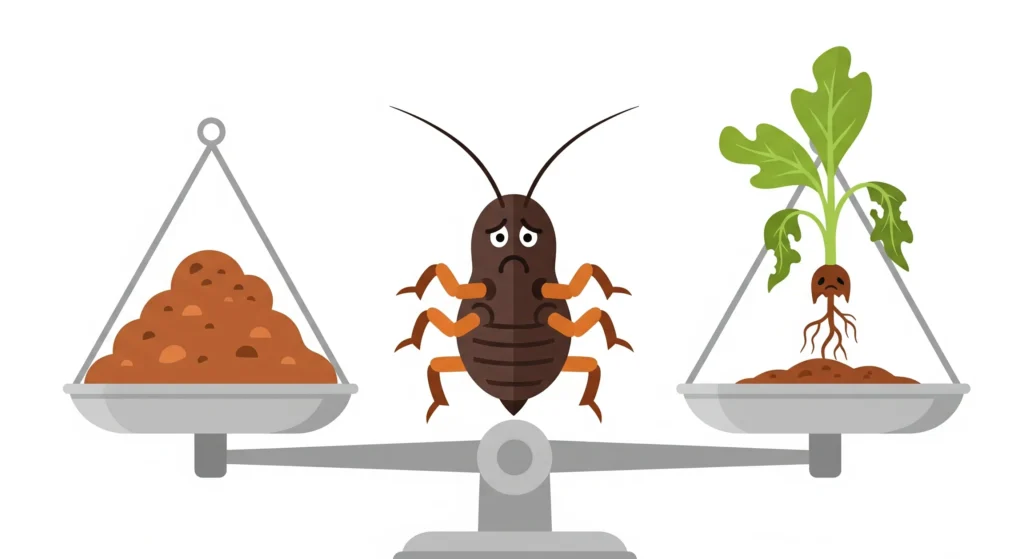
土の中にいるケラは、私たちの生活にとって良い存在なのでしょうか、それとも悪い存在なのでしょうか。実は、ケラは「益虫」と「害虫」の両方の側面を持っています。
益虫としての側面
ケラが土を掘り進むことで、土壌が耕されて柔らかくなり、通気性や水はけが良くなります。これは植物の根が育ちやすい環境を作る手助けとなり、一種の「土壌改良」の効果が期待できます。
害虫としての側面
一方で、特に農業や家庭菜園においては害虫として扱われることがあります。ケラは雑食性で、植物の根や種、球根などを食べてしまうことがあります。特に、植えたばかりの苗や、芝生、ヤマトイモやサツマイモといった根菜類が被害に遭いやすいです[2]。トンネルを掘る際に根を傷つけてしまい、植物が枯れる原因になることもあります。
家庭菜園でできるケラの対策・駆除方法

ケラによる被害を防ぐためには、まず「寄せ付けない環境づくり」が基本です。
ケラを寄せ付けない環境づくり
ケラは有機物(腐葉土や堆肥)が豊富で、湿った土を好みます。
| 対策 | 注意事項 |
|---|---|
| 未熟な堆肥の使用を避ける | 発酵が不十分な堆肥はケラの餌や産卵場所になりやすいため、完熟した堆肥を使いましょう。 |
| 水はけを良くする | 畑の畝(うね)を高くするなどして、土壌が過度に湿った状態にならないように管理します。 |
| 苗の周りをガードする | 植えたばかりの苗は特に狙われやすいため、牛乳パックやペットボトルを輪切りにしたものを地面に刺し、物理的にガードするのも効果的です。 |
ケラは益虫としての側面もあるため、多少見かける程度であれば、過度に駆除する必要はありません。植物に明らかな被害が出始めた場合に、対策を検討しましょう。
被害が深刻な場合の駆除方法
どうしても被害が収まらず、植物が全滅するような深刻な状況では、薬剤の使用も選択肢の一つとなります。
家庭菜園で使えるケラに対応した殺虫剤が、園芸店やホームセンターで販売されています。使用する際は、必ず製品のラベルに記載されている使用方法、対象植物、使用量を厳守してください。特に野菜に使用する場合は、収穫までの期間(使用禁止期間)が定められていることが多いので、十分に注意が必要です。
ケラに関するQ&A
Q1. ケラに毒はある?触っても平気?
A1. ケラに毒はありません。見た目が少しユニークなので不安に思うかもしれませんが、毒を持っておらず、人を刺したり咬んだりすることも基本的にはありません。素手で触っても問題ありませんが、土を掘る前足の力が意外に強いので、少し驚くかもしれません。衛生面を考え、どんな虫を触った後でも手を洗うことをおすすめします。
Q2. ケラの寿命はどのくらい?
A2. 成虫としての寿命は約1年ほどと言われています。ケラは卵から幼虫を経て成虫になるまでにも1〜2年ほどかかるため、一生涯としては2〜3年を土の中で過ごすことになります。
Q3. 「おけら」って何のこと?
A3. 「おけら」はケラの別名です。特に東日本ではこの名前で呼ばれることが多いようです。ちなみに、「所持金がなくなること」を意味する「おけらになる」という慣用句があります。これは、ケラが前足を広げて万歳しているように見える姿から、「お手上げ」を連想して生まれた言葉だと言われています。
まとめ
今回は、謎多き昆虫「ケラ」について、その生態から対策までを詳しく解説しました。
- ケラの正体は「バッタ目・ケラ科」の昆虫
- モグラのような前足が最大の特徴
- 「掘る・飛ぶ・泳ぐ」という多彩な能力を持つ
- 地面から聞こえる「ジー」という音はオスの鳴き声
- 土を耕す益虫の面と、作物の根を食べる害虫の面がある
- 対策は「寄せ付けない環境づくり」が基本
ケラは、私たちの足元の土の中で、人知れずユニークな生活を営んでいます。その生態を正しく理解し、被害が大きい場合は適切に対処しながら、上手に付き合っていきましょう。
参考文献
- [1] 国土交通省 筑後川河川事務所 – 陸上昆虫類等 ケラ
- [2] J-STAGE – ケラによるヤマトイモの被害と防止対策
- [3] 熊本市動植物園 – 資料館つれづれNo.44『ムシムシ観察記ーケラの巻①』
筆者
尾古葉典彦
投稿者
norihiko.ookoba@outlook.jp







